
全国各地に設置されている堆肥センターでは、家畜糞や剪定枝などの有機廃棄物を回収し、発酵させて農業用堆肥として再利用する事業を行っている。数年前からこれら堆肥センターの建物及び強制発酵用攪拌機架台の防食対策として亜鉛めっき処理が施されるようになってきているので、現状における亜鉛めっきの耐久性を評価するための調査を行った。
1.調査概要
調査対象:
上村堆肥センターH形鋼柱及び発酵室攪拌機
所 在 地:
熊本県球磨郡上村神殿原2-170
建設時期:
平成7年3月
調査年月日:
平成15年3月18日
2.施設概況
熊本県南部の人吉盆地の中にあり、鹿児島県境にも近い静かな環境にある。周辺は農地が多く、自然環境としては田園地帯である。大気汚染による腐食は少ないと考えられるが、本施設は周辺農家からの牛糞、鶏糞等を集めて堆肥化しているため、これらの原料から発生するアンモニア性ガスと発酵熱による水蒸気の発生が多く、内部の環境はかなり厳しい。
3.調査内容
(1)外観観察
建設後8年を経過しているが、外部露出している部分の亜鉛めっき皮膜はほとんど腐食が進行していない。発酵室棟内部ではアンモニア性ガスを含んだ水蒸気が屋根で凝結して落下するため、床面に部分的な水溜りを生じている。亜鉛めっきH形鋼柱のうち、この水溜りと接触している根元部分はペースト状の堆肥微粉に覆われているため表面観察はできないが、それ以外の部分は発酵室棟内部でも特に異常は認められなかった。
養生槽棟及び製品貯留棟のH形鋼柱は色調、平滑度ともに均一で、外観上腐食が進行している兆候はみられない。なお撹拌機架台に取付けられている飛散防止板は赤褐色の汚れのほかに、一部赤錆と見られる部分もあったが、物理的損耗を考慮して交換部品的目的で取付けられているとのことであり詳細な調査は行わなかった。
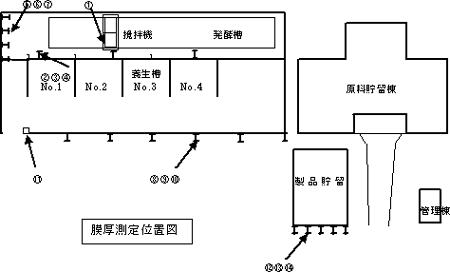
(2)膜厚測定
[1] 測定方法
現地で測定箇所を決め(上図参照)、測定点を中心に約10cm四方をサンドペーパーで研磨し、電磁膜厚計により10cm角の中を10点測定した。




[2] 膜厚測定結果
| No | 名称 | 平均膜厚 | No | 名称 | 平均膜厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 攪拌機架台 | 135.1 | (8) | 養生棟H柱F | 100.0 |
| (2) | 発酵棟壁側H柱F | 112.1 | (9) | 養生棟H柱W1 | 115.2 |
| (3) | 発酵棟壁側H柱W1 | 126.0 | (10) | 養生棟H柱W2 | 101.8 |
| (4) | 発酵棟壁側H柱W2 | 111.4 | (11) | シャッター角柱下 | 89.8 |
| (5) | 発酵棟窓側H柱F | 102.9 | (12) | 貯留棟H柱F | 89.9 |
| (6) | 発酵棟窓側H柱W1 | 100.0 | (13) | 貯留棟H柱W1 | 97.5 |
| (7) | 発酵棟窓側H柱W2 | 91.3 | (14) | 貯留棟H柱W2 | 92.3 |
F:フランジ W:ウェブ 単位:μm
4.まとめ
建屋のH形鋼柱と発酵室撹拌機の架台の亜鉛めっき膜厚を測定し、いずれも十分なめっき皮膜を形成していることがわかった。攪拌機架台はアンモニア性ガスを含む水蒸気に曝されることから、最も厳しい腐食環境にあると思われたが、亜鉛めっき膜厚が約135μmあり、耐久性の点ではまだ数十年はメンテナンス不要と考えられる。コンクリート床に溜まった結露水にふれる柱の根元部分は、現状では汚れ以外に特に異常は見られないが、適当な時期にジンクリッチペイントなどによる補修塗装を施しておけば今後とも十分耐久性を維持することが可能である。
